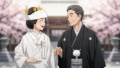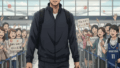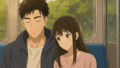日本バスケ界を牽引するポイントガード、テーブス海選手。彼が履いているバッシュ、気になりますよね。
Bリーグや日本代表での華麗なプレーを見るたび、「あのバッシュは何だろう?」「どこのモデル?」と目で追ってしまう人も多いんじゃないでしょうか。特にオリンピックのような大舞台で彼が履いていた一足は注目を集めました。
テーブス選手といえばアディダスとの関係が深いですが、歴代でどんなモデルを履いてきたのか、なぜトレイヤングのモデルを選んだのか。また、河村勇輝選手や富樫勇樹選手といった他のトップガードがアシックスやコンバースを選ぶ中で、テーブス選手の選択はどう違うのか。
この記事では、そんなテーブス海のバッシュに関する情報をまとめ、彼のプレースタイルとシューズの関係性、そして気になるサイズ感などについても触れていきたいと思います。
- テーブス選手とアディダスの長年の関係性
- なぜローカットモデル「トレイヤング1」を選んだか
- トレイヤング1の詳しい性能とサイズ感
- 河村勇輝選手などライバルとのバッシュ比較
テーブス海 バッシュのこだわり徹底解剖

まずは、テーブス選手が愛用するバッシュの核心部分、アディダスとの関係性や彼固有のこだわりに迫っていきます。彼がなぜその一足を選び、履きこなしているのか、その背景が見えてくるかもしれませんね。
テーブス海とアディダスの深い関係
テーブス選手とアディダスの関係は、プロになってから始まったものではないんです。
彼自身が語っているように、「ずっと高校生の時からアディダスにすごいよくしてもらって」いたそうで、本当に長いお付き合いみたいですね。アメリカ挑戦時代から含め、キャリアの重要な時期を共に過ごしてきたブランドというわけです。
弟のテーブス流河選手もアディダスと契約しており、家族ぐるみでの信頼関係が伺えます。単なるスポンサー契約という言葉以上に、彼のパフォーマンスを深く理解し、支え続けてきたパートナーという感じがします。
補足:信頼関係がシューズ選びに与える影響
これだけ長い間サポートを受けていると、ブランド側も選手の足の癖や好みを熟知しているでしょうし、選手側も製品の特性を深く理解しているはずです。この信頼関係が、彼のパフォーマンスを最大限に引き出すシューズ選びに繋がっているのは間違いないかなと思います。
なぜローカットモデルを好むのか
テーブス選手のバッシュ選びで最も特徴的なのは、一貫してローカットモデルを好んでいる点です。
彼は自身の足が「細い方」だと認識していて、フィット感を非常に重視していると公言しています。その上でローカットを選ぶのは、やはり彼のプレースタイルと直結しているんでしょうね。
ポイントガードとして、俊敏な方向転換やスピードの緩急、そしてドライブからの広い視野を活かしたパスが求められます。ローカットは足首の可動域を最大限に確保できるため、彼の持ち味である「ゲームコントロールとスピード」を邪魔しない、むしろブーストしてくれる存在なんだと思います。
ミドルカットやハイカットの安心感よりも、足首の自由度を優先する。これは、彼のプレースタイルへの自信の表れとも言えるかもしれません。
オリンピックで着用した一足
日本代表としてパリオリンピックの舞台でも活躍したテーブス選手。あの世界最高峰の舞台で彼の足元を支えていたのが、「adidas TRAE YOUNG 1(トレイヤング1)」でした。
これは、NBAアトランタ・ホークスのスター、トレイ・ヤングの初代シグネチャーモデルです。トレイ・ヤングもまた、創造性あふれるパスとドライブ、そして深いシュートレンジを持つポイントガード。プレースタイルに共通点のある選手のモデルを選ぶというのは、とても理にかなっていますよね。
トップアスリートが、自分と似た動きを想定して作られたシューズを選ぶ。これは、私たち一般のプレイヤーがバッシュを選ぶ上でも非常に参考になる視点かなと思います。
主力モデル:トレイヤング1を分析
では、彼が選んだ「トレイヤング1」とは、具体的にどんなシューズなのでしょうか。
最大の特徴は、シューレース(靴紐)の穴がたった2箇所しかない、ユニークな「セミレースレス」構造です。アッパー全体が一体型のブーティー構造になっていて、足を包み込むようなフィット感を目指して設計されています。
これは、従来のバッシュのように「紐でガチガチに縛り上げる」という感覚とは少し異なるかもしれません。どちらかというと、ソックスのように足とシューズの一体感を高めることを重視したデザインですね。
トレイヤング1の性能とクッション
パフォーマンス面で注目すべきは、クッショニングとグリップ力です。
2種類のクッションを組み合わせたハイブリッド構造
「トレイヤング1」のミッドソールは、2つの異なる素材で構成されています。
- Lightstrike(ライトストライク): ミッドソール全体に使われている軽量フォーム。反発性が高く、コートの感覚をダイレクトに足裏に伝えてくれる(コートフィールが良い)のが特徴です。素早い動き出しをサポートします。
- BOOST(ブースト): かかと部分に戦略的に埋め込まれています。こちらはアディダスが誇る衝撃吸収素材。ジャンプからの着地など、強い衝撃から足を守ってくれます。
つまり、「前足部で素早く動き、かかとでしっかり衝撃を吸収する」という、ガードプレーヤーの理想的な動きをサポートする設計になっているんですね。
強力なグリップ力
アウトソールには、伝統的で信頼性の高い「ヘリンボーンパターン」が採用されています。レビューなどを見ても、「止まりすぎるくらい効く」と評されるほど、グリップ性能は非常に高いようです。テーブス選手の鋭いドライブや急ストップは、この強力なトラクションによって支えられている部分も大きいでしょう。
トレイヤング1のサイズ感とフィット
「トレイヤング1」は、非常に特徴的なシューズなだけに、フィット感については評価が分かれるポイントでもあります。購入を検討する際は、特に注意が必要かもしれません。
注意:サイズ選びとフィット感のクセ
多くのレビューで指摘されているのが、「かかとのホールド感(ロックダウン)が少し弱い」という点と、「サイズ感がやや大きめ」という点です。
独特のセミレースレス構造のため、人によってはかかとが浮くような感覚を覚えることがあるようです。また、全体的に大きめの作りのため、普段のサイズからハーフサイズ(0.5cm)ダウンを推奨する声が多く見られます。
テーブス選手自身は「足幅が細い」と語っています。もしかすると、彼の足の形がこのシューズのラスト(足型)にたまたま合っていたか、あるいは、彼は卓越したグリップ性能とコートフィールを優先し、フィット感のわずかな懸念点(もしあったとして)を許容しているのかもしれませんね。
購入を検討する方へ
このシューズは、現在では主にアウトレットやリセール市場での流通が中心となっています。もし試着できる機会があれば、必ず両足を履いて、できればハーフサイズ下も試してみることを強くおすすめします。
テーブス海 バッシュとライバル比較
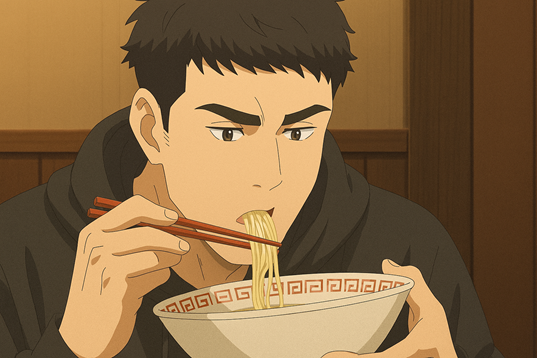
テーブス選手がアディダスの「トレイヤング1」を選ぶ一方で、Bリーグの他のトップポイントガードたちは、また異なるブランドのシューズを選んでいます。この比較から、各ブランドの哲学や選手の好みの違いが見えてきて面白いですよ。
最新モデルAE1との違い
アディダス内で比較しても、選択肢は「トレイヤング1」だけではありません。今、最も注目されているアディダスのバッシュといえば、アンソニー・エドワーズの「AE 1」でしょう。
「AE 1」は、ハニカム状のケージがアッパーを覆う未来的なデザインと、フルレングスの「Jet Boost」によるソフトで反発性の高いクッショニングが特徴です。「トレイヤング1」がコートフィール重視のハイブリッドだったのに対し、「AE 1」はよりクッション性とホールド感を重視したモデルと言えます。
テーブス選手が「AE 1」ではなく「トレイヤング1」を選んでいる(もしくは履いていた)のは、彼がソフトすぎるクッションよりも、ダイレクトな接地感と軽量性を優先しているからかもしれませんね。
ハーデンやデイムモデルとの比較
アディダスには他にも強力なシグネチャーラインがあります。
- ハーデンシリーズ: ジェームズ・ハーデンのモデル。ステップバックなど横の動きに対応するため、安定性とクッショニングを最大限重視する傾向があります。
- デイムシリーズ: デイミアン・リラードのモデル。安定した接地感と確実なロックダウンを優先し、バランス型とされることが多いです。
これらのモデルと比較しても、「トレイヤング1」は「前足部のダイレクト感」と「かかとの衝撃吸収」という、特定のニーズに特化したハイブリッドな選択肢だったことがわかります。テーブス選手は、自分のプレーに最も必要な要素をピンポイントで選んだ、と言えそうです。
歴代の着用シューズまとめ
テーブス選手はキャリアの早い段階からアディダスと深いつながりを持っています。プロ入り前からアディダスのシューズを愛用しており、宇都宮ブレックス時代、滋賀レイクス時代、そして現在のアルバルク東京に至るまで、一貫してアディダスの様々なモデルを履きこなしてきました。
特定のモデルに固執するというよりは、その時々のアディダスのラインナップ(デイムシリーズやハーデンシリーズ、そして今回のトレイヤングシリーズなど)の中から、自身のコンディションやプレースタイルに最もフィットするローカットモデルを選び続けている、という印象ですね。
河村勇輝のバッシュ(アシックス)
テーブス選手と並び称される日本最強のガード、河村勇輝選手(横浜ビー・コルセアーズ)が選ぶのは、アシックス(Asics)です。
彼が愛用するのは「UNPRE ARS LOW 2(アンプレ アルス ロー 2)」など。彼もテーブス選手と同様に、足首の自由度を最優先するローカット愛好家です。
アシックスのシューズ、特に「UNPRE ARS」シリーズは、急な切り返し(カッティング)の際に足がシューズの外側に流れてしまうのを防ぐための「サイドウォール構造」が特徴です。日本のブランドらしく、日本人の足型に合わせたフィット感と、怪我を防ぐための安定性・安全性を非常に重視しています。
グローバルなテクノロジーを追求するアディダス(テーブス選手)と、フィット感と安定性を追求するアシックス(河村選手)。二人の選択は、ブランドの哲学の違いを体現しているようで興味深いですね。
富樫勇樹のバッシュ(コンバース)
もう一人のトップガード、富樫勇樹選手(千葉ジェッツ)はコンバース(Converse)と契約しています。
彼が履くのは、パフォーマンスモデルの「CONS VICBOUND」など。コンバースは、ブランドが持つ伝統的なスタイルと、現代のバスケットボールに必要なテクノロジーを融合させるアプローチを取っています。
富樫選手の超高速なプレースタイルを支えるため、安定したミッドソールや通気性の良いアッパーを備えています。これは、テクノロジー主導のアディダスやアシックスとはまた違う、「ヘリテージ(伝統)とパフォーマンスの融合」という独自の立ち位置を狙った戦略と言えるでしょう。
トップガード3人の選択
- テーブス海 (アディダス): テクノロジー主導型(ハイブリッド)
- 河村勇輝 (アシックス): フィット・安定性追求型(国内)
- 富樫勇樹 (コンバース): ヘリテージ・復権型
どの選手のスタイルに共感するかで、選ぶバッシュの哲学も変わってくるかもしれませんね。
まとめ:テーブス海 バッシュの選び方

ここまで見てきたように、テーブス海選手のバッシュ選びは、彼のプレースタイルとアディダスへの深い信頼に裏打ちされた、非常にロジカルなものでした。
テーブス選手のバッシュ選びのポイント
- ローカット一択: 足首の自由度を最優先し、スピードと俊敏性を活かす。
- コートフィール重視: クッション性も必要だが、それ以上に前足部のダイレクトな接地感を重視する(トレイヤング1のLightstrike)。
- 信頼するブランド: 高校時代から続くアディダスとの関係。
- トレードオフの許容: トラクションやコートフィールという絶対的な長所のために、フィット感のクセ(トレイヤング1のかかと)は許容、もしくは彼にとっては問題ない可能性。
私たち一般プレイヤーが「テーブス海 バッシュ」と同じモデルを選ぶ際は、彼のこだわりを参考にしつつも、自分の足型やプレースタイルと相談することが重要ですね。
特に「トレイヤング1」のような特徴的なモデルは、必ず試着して、サイズ感(ハーフサイズダウン推奨)やかかとのフィット感を確かめることをお勧めします。
この記事で紹介した情報は、あくまでシューズ選びの一助とするものです。最終的な判断は、ご自身の足で試着した感覚を最優先してくださいね。